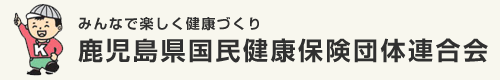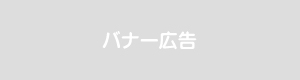教えて健康法
第6回 ストレスへの対処法 ~俯かん的視点と相談の効果~ -教えて健康法 メンタルヘルス編-
ストレスは特別なことによって引き起こされるわけではなく、私たちの日常生活や環境の中にあります。通常、私たちは何らかのかたちでストレスを上手に発散しています。
それは、私たちのからだには、ゴムマリのような弾力でストレスを跳ね返そうとする働きがあるからです。
しかし、その頑張りも長く続くと弾力性は失われ、自分ではどうにもできなくなって「心や体の病気」になることがあります。
ストレスがもとで心身に影響が出ている場合には、その原因であるストレッサーを取り除くことが解決への早道ですが、上手に気分転換をしたり、日頃から自分に合ったストレス対処法をいくつか身につけることで、ストレス回避を図ることもできます。
第5回 睡眠とメンタルヘルス ~睡眠の質を高めるポイント~ -教えて健康法 メンタルヘルス編-
現代人は睡眠不足
日本人の睡眠時間は世界で最も短いといわれています。(表1)
加えて、コロナ禍の外出自粛や加速するデジタル化など、環境や生活の変化から睡眠のリズムが崩れてしまったという人は少なくないのではないでしょうか。
睡眠不足は、短期的には全身の倦怠感やパフォーマンスの低下をまねき、自律神経のバランスを崩してしまいます。
自律神経が乱れると、「朝起きられない」、「寝ても疲れがとれない」、「夜なかなか眠れない」などの症状につながり、睡眠不足が負債のようにたまると、生活習慣病やがん、認知症、うつ病などのリスクが高まることがわかっています。
第4回 食生活とメンタルヘルス ~小腹が空いたらタンパク質を~ -教えて健康法 メンタルヘルス編-
朝食は体内時計を整えるカギ
近年、食生活とメンタルヘルスに関する研究において、食事をとる「タイミング」や「何を食べるか」といったことは、身体だけでなく心の健康にもかかわることがわかってきています。
特に、メンタルヘルスケアとして、食事を通じ、「体内時計」のリズムを正しく保つことを意識することはとても重要です。
私たち人間には1日周期でリズムを刻む体内時計が備わっており、意識しなくても昼間は身体と心が「活動状態」に、夜間は「休息状態」に切り替わります。
体内時計が乱れると、メンタルヘルスに関わるホルモンの分泌や、自律神経の働きにも影響を与えることが指摘されています。
体内時計に最も強く影響するのは「光」の刺激ですが、「食事」も重要な要素のひとつと考えられています。
なかでも「朝食」は体内時計を整えるカギと言われています。
第3回 運動とこころの健康~からだを動かしこころの充電を~ -教えて健康法 メンタルヘルス編-
こころと身体はつながっている
『♪最近ストレッチを怠っているからかなぁ?上手く開けないんだ心がぎこちなくてOh♪』
これは、日本の人気ロックバンドMr.children(ミスターチルドレン)の「箒星(ほうきぼし)」という曲の歌詞の一部です。
2007年に発売され、流行したこの曲を皆さんご存知でしょうか。
「ストレッチを怠ると心が上手く開けない」という歌詞は、ストレッチを怠ると身体は硬直し、身体が硬いと心も硬く閉ざしてしまうという、まさに心と身体はつながっていることを端的に表わしていると感じた一文です。
第2回 「ストレスチェックと働く人のメンタルヘルス」-教えて健康法 メンタルヘルス編-
ストレスは気づきにくい
わたしたちにかかるストレス要因はひとつではありません。複数の要因が重なって、また、一人ひとりの受け止め方によってストレスの強さは異なります。ストレスには個人差があり、あなたにとってたいしたことはなくても、他の人にはとてもつらいストレスになることもあります。
また、ストレスは当人に必ずしもストレスとして自覚されているわけではありません。
第1回 「ストレス」と「メンタルヘルス不調」-教えて健康法 メンタルヘルス編-
はじめに
新型コロナウィルス感染症が日本でも拡大して以来、長引く感染に対する不安を抱えながら、行動制限等の対策により、私たちは大きな変化を迫られました。
令和3年3月、厚生労働省から報告された「新型コロナウィルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査」によると、「そわそわ、落ち着かなくなった」等、実に7割近くの人が、環境の変化に伴い心理面に多大な影響があったと回答しています。(図1)
こうした心理面の変調は多くの人が抱えており、近年、こころの健康づくり(メンタルヘルス)は身近なテーマとなっています。
第6回 「フレイル予防のための運動」-教えて健康法 運動による疾病予防編-
フレイルとは
「フレイル」とは、英語の“Frailty”をかな表記したもので、“虚弱”や“老衰”などと言われてきた状態を意味します。フレイルは、足腰が弱くなって筋力が衰えて転びやすくなるといった身体的問題だけではなく、認知機能障害やうつなどの精神・心理的問題、独居や経済的困窮などの社会的問題を含む多面性を有する概念であるとされています(図1)。 とくに、身体的な衰えを有する身体的フレイルに該当すると、近い将来に介護が必要になるリスクが高まります。つまり、フレイルは生活機能障害、要介護状態、死亡などの転帰に陥りやすい状態で、健常と要介護の中間にも位置づけられます。しかし、フレイルは悪化する一方ではなく、しかるべき対応で改善が期待できます。可逆性を有することが特徴のひとつです。そのため、フレイルの早期発見、早期対処が非常に重要となります。
第5回 「糖尿病予防のための運動」-教えて健康法 運動による疾病予防編-
糖尿病の分類
糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)が多くなる病気で、血液中のブドウ糖の割合は血糖値と呼ばれます。空腹時の血糖値が126㎎/dl以上、または食事に関係なく血糖値が200㎎/dl以上となると糖尿病の基準に該当します。また、HbA1c値は過去1~2か月間の平均血糖値を反映しているとされ、HbA1c値が6.5%以上で糖尿病の診断基準に該当します。 一般的に知られている糖尿病には、「1型糖尿病」と「2型糖尿病」があり、日本では95%以上の糖尿病患者が2型糖尿病とされています。2型糖尿病は、いくつかの遺伝因子と過食(食べすぎ)、運動不足、ストレスなどの生活習慣が加わり、インスリンの働きが悪くなり、糖尿病を発症します。インスリンは、膵臓から分泌されるホルモンで、ブドウ糖を体内に取り込んで蓄え、エネルギー源として使うことができる状態にしてくれます。インスリンの働きによって、血糖値は一定の範囲内におさまっています。 糖尿病の初期には喉の渇き、頻尿、手足の感覚低下などがあらわれることがありますが、初期段階では自覚症状がまったくないことが多いとされています。重症化すると、3大合併症として神経障害、網膜症、腎症を発症することが知られています。また、動脈硬化による脳卒中や心臓病の危険が高まる他、認知症の危険も高くなります。
第4回 「認知症予防のための運動」-教えて健康法 運動による疾病予防編-
認知症の危険因子
世界の認知症患者は4680万人(2015年)と推計されており、2030年には7470万人、2050年には1億3250万人まで増加すると予測されています。わが国においては、要介護の原因の第1位が認知症となっています(基礎調査)(図1)。糖尿病、高血圧、肥満、喫煙、うつなどの生活習慣に関わる要因は、認知症の重大な危険因子となります。そのため、これらの生活習慣病を予防し、適切に管理することは、認知症予防のためにも重要となります(図2)。 とくに身体活動が不足することは、認知症の発症や認知機能の低下に強く関連します。つまり、運動によって身体活動を向上させて活動的なライフスタイルを確立することは、認知機能の低下を抑制するために非常に重要です。
第3回「メタボリックシンドロームの予防のための運動」-教えて健康法 運動による疾病予防編-
メタボリックシンドロームとは?
メタボリックシンドロームとは、内臓のまわりに脂肪が過剰に蓄積した状態を前提に、高血圧、血清脂質異常、高血糖のいずれか2つ以上をあわせもった状態を示し、動脈硬化を進行させてしまい、心臓病や脳卒中などになりやすい病態とされます。通称、「メタボ」と言われます。日本では、図1に示すような基準を用いて診断されます。メタボリックは「代謝」、シンドロームは「症候群」を意味しますので、直訳すると代謝症候群となりますが、代謝とは直接的には関係しない高血圧も主要な項目に含まれ、国内でも名称が定着してきていますので、メタボリックシンドロームと表記するのが一般的です。CTスキャンによる臍の位置での内臓脂肪面積が100cm2以上で、内臓脂肪の蓄積による悪影響が顕著とされており、内臓脂肪面積100cm2を基準にウエストサイズに換算すると男性85㎝、女性90㎝が算出され、これらの値が用いられています。